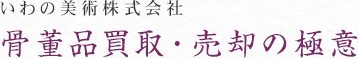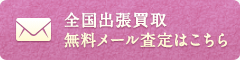沖縄県に伝わる伝統工芸品の一つである琉球漆器(りゅうきゅうしっき)は、南国という土地柄を反映した、明るい朱色や堆錦(ついきん)という独特の技法が特徴です。
艶のある黒地や、明るい朱色にハイビスカスや県花のデイゴの花模様、琉球螺鈿と呼ばれる螺鈿細工が施された皿や椀など、輪島漆や木曽漆器とはひと味違った、沖縄らしさが魅力です。
 琉球漆器という名は、昭和49年に伝統的工芸産業の振興に関する法律が制定された際に、輪島塗、山中漆器、津軽塗などと同様にこの呼び方になり、現在は、沖縄県指定伝統工芸品、経済産業大臣指定伝統的工芸品にも指定されています。
琉球漆器という名は、昭和49年に伝統的工芸産業の振興に関する法律が制定された際に、輪島塗、山中漆器、津軽塗などと同様にこの呼び方になり、現在は、沖縄県指定伝統工芸品、経済産業大臣指定伝統的工芸品にも指定されています。
漆器を乾燥するには適度な温度と湿度が必要ですが、沖縄の気候は年平均気温22.4℃、湿度77%と、漆器には非常に適した環境です。日本の他の漆器の産地とは異なり、乾燥の際に、温度や湿度を調節する必要のない、漆器には適した自然の条件が、沖縄には整っています。琉球漆器の木地には、エゴノキ、センダン、ガジュマルなどが使われます。
 琉球漆器の製作がいつ頃から始まったのは、はっきりしていませんが、琉球王朝時代に周辺諸国との外交記録が収録された「歴代宝案」には、各国への進貢品としての漆工品が記載されており、中国との貿易が盛んであった14〜15世紀頃には、琉球で漆工芸の技術が確立されていたと考えられています。
琉球漆器の製作がいつ頃から始まったのは、はっきりしていませんが、琉球王朝時代に周辺諸国との外交記録が収録された「歴代宝案」には、各国への進貢品としての漆工品が記載されており、中国との貿易が盛んであった14〜15世紀頃には、琉球で漆工芸の技術が確立されていたと考えられています。
琉球漆器は、貿易立国であった琉球王朝にとって重要な輸出品でした。また、琉球漆器は、貿易品としてだけでなく、美術工芸品としても大変優れていたため、中国への進貢品や、将軍家への献上品としても、最も喜ばれた品物のひとつでした。
また、琉球の貴族階級も生活用品として漆器を取り入れるようになり、宮廷舞踊などの文化面においても、漆器は重要な役割を果たしていました。
琉球王朝時代には、技術者を中国へ派遣し、螺鈿、沈金、箔絵などの漆芸技法ももたらされました。特に、1715年に比嘉乗昌が中国に加飾法を学び、「堆錦(ついきん)」という独自の技法を生み出しだしたことは琉球漆器の発展に大きく影響し、今日ではこの堆錦が琉球漆器の主流を占めています。
 また、15世紀に統一された琉球王国の王府は、直営の漆器製作所として「貝摺奉行所」を設け、手厚い庇護のもと、漆器の生産管理を行わせました。
また、15世紀に統一された琉球王国の王府は、直営の漆器製作所として「貝摺奉行所」を設け、手厚い庇護のもと、漆器の生産管理を行わせました。
琉球漆器のひとつに近海で採れた夜光貝を磨いてつくる「螺鈿漆器」がありますが、貝摺奉行所の名称はこれに由来するとされています。
1609年以降、琉球が事実上、薩摩藩に支配されるようになると、琉球漆器のデザインは中国風となり、箱書きも中国語で書かれ、唐物として日本へ輸入された時期もあったといいます。
 明治時代に入ると、琉球王国が廃止され沖縄県になると、貝摺奉行所など琉球王府の保護政策の時代は終わり、漆器製作は民間の工房が行うようになりました。こうした工房が集まって、那覇市若狭に塗物街などもできました。
明治時代に入ると、琉球王国が廃止され沖縄県になると、貝摺奉行所など琉球王府の保護政策の時代は終わり、漆器製作は民間の工房が行うようになりました。こうした工房が集まって、那覇市若狭に塗物街などもできました。
大阪や鹿児島の商人が問屋としてかかわるようになり、盆、膳、椀、硯箱など本土向けの製品がつくられました。
このころは、琉球王朝時代の美術工芸品な意味合いの作品よりも、日用品が主体で、絵柄も松竹梅や鶴亀などのデザインが多くみられます。丈夫な漆器であることと実用性も相まって琉球漆器は人気を博すようになり、多くの漆工職人がいましたが、沖縄戦を経て破たん・消失しました。
戦後、琉球漆器は沖縄の米軍基地関係者への土産品として再興され、従来の朱塗り中心であったものが、黒塗り中心となり、真っ赤なハイビスカスなどが描かれたエキゾチックで神秘的な作品が駐留軍向けの土産物として喜ばれました。
1977年には琉球漆器事業協同組合が設けられ、琉球漆器の伝統的な朱塗りと黒塗りのコントラストの大胆さ、斬新さ、鮮明さは、現在も多くの人に親しまれ続けています。