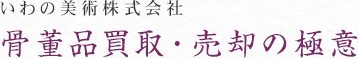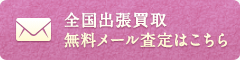磁器の王様ともいわれるのがボーンチャイナ(BONE CHINA)。洋食器のバックサインに「BONE CHINA」と記されているものを見かけたこともあるかもしれませんね。「ボーン」=骨、「チャイナ」=磁器を指しています。
ボーンチャイナは、磁器の素地に動物の骨灰を混ぜて胎土として焼成した硬質磁器と軟質磁器の中間に位置するものです。
焼成温度は約1050℃と低いですが、光に当てると、生地が透けるような高い透光性を備え、美しい柔らかな艶が特徴です。
 ボーンチャイナは陶器や白磁器に比べると、比較的新しい焼き物です。1748年、アイルランド出身で、当時版画家・肖像画家として知られたトーマス・フライが英国ロンドン東部のボウ窯で、磁器の胎土に骨灰を使用する特許を申請し、これがボーンチャイナの誕生の日とされています。
ボーンチャイナは陶器や白磁器に比べると、比較的新しい焼き物です。1748年、アイルランド出身で、当時版画家・肖像画家として知られたトーマス・フライが英国ロンドン東部のボウ窯で、磁器の胎土に骨灰を使用する特許を申請し、これがボーンチャイナの誕生の日とされています。

当時、ヨーロッパではシノワズリという中国趣味の流行や、日本風を好んだジャポニズムの影響もあって、東洋の白磁器に対する強い憧れをもっていました。
しかし、イギリスでは、古来、白磁器をつくる粘土(長石)などの原料がほとんど入手出来なかったため、白い磁器を作ることが出来ませんでした。
そこで、ボウ窯のトーマス・フライが、原料に牛骨灰(BONE ASH)を使用して、貴婦人のような肌合いの美しい素地の乳白色の磁器を作ることに成功し、これによって白磁器とは異なった温かみのあるクリーミーなイギリス独特のボーンチャイナが誕生したのです。しかし、実際にボーンチャイナが製作されたのは、1749年以降であったといわれています。
牛の骨灰は、リン酸三カルシウム含有量の高さと鉄分が少ないことから、最も美しく仕上がるそうです。素地に骨灰を入れる割合は、はじめ40%前後でした。骨の粉を全体の50%以上含んでいる器は「ファインボーンチャイナ」と呼ばれ、ボーンチャイナの最高級品として受け継がれてきました。
18世紀後半、スタッフォードシャーのスポード2世、ウェッジウッド2世、少し遅れてウースター窯のバールらが骨灰にカオリンや粘土を混ぜて、胎土の改良に努め、ボーンチャイナは19世紀のイギリスのテーブルウェアの主流となりました。
 ボーンチャイナの特徴は何といっても、繊細でキメ細かい素地の色と艶です。
ボーンチャイナの特徴は何といっても、繊細でキメ細かい素地の色と艶です。
クリーミー・ボーンチャイナと評されるほどの美しさを持っています。
また、ボーンチャイナの素地は、透過性が高く、やさしく叩くと、キーンという高い音が響きます。古来、ボーンチャイナは光を通す性質から、ランプシェードとしても使われてきました。
そして、ボーンチャイナは真正磁器に比べ、柔らかいですが、軟質磁器よりも耐久性があります。
しかし、骨灰を多く含んだボーンチャイナは、素地土に粘土質の割合が低く、素材の可塑性(=ねばり)が無いため、細かい作業が難しく、レースのような縁取りや、スカシ模様などは苦手で、型による鋳込成形が大部分を占めています。
ボーンチャイナは、本焼きを済ませた後、仕上げにガラス粉末を調合した特殊な釉薬を器の表面に塗り、二次焼成を行い低温で器に定着させます。そのため、ボーンチャイナは、白磁器に比べ、多くの顔料を用いた華やかな色調の作品をつくることができ、その表面はとても滑らかで、鏡のように美しい、上質な高級感を持っています。
温かみのある乳白色と滑らかな質感、美しい透光性を特徴とする最高級の磁器といわれたボーンチャイナは、英国の伝統的なアフタヌーンティーに欠かせない洋食器であり、イギリスアンティーク食器の定番として、50年、100年前のボーンチャイナが大切に扱われています。

ウェッジウッド(Wedgwood)
ロイヤルドルトン(Royal Doulton)
ミントン(Minton)
スポード(Spode)
ロイヤルウースター(Royal Worcester)
ロイヤルクラウンダービー( Royal Crown Derby )など
日本では、鳴海製陶、大倉陶園、ノリタケカンパニーリミテドなどがボーンチャイナを手掛けています。