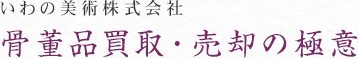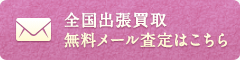17世紀から18世紀にかけてヨーロッパの近世陶芸に大きな足跡を残したデルフト陶器。デルフト陶器(またはデルフト焼)とは、オランダのデルフトにてつくられる軟質陶器です。
 デルフト陶器のルーツは、16世紀にイタリアのマジョルカ出身の陶工グィド・ディ・サビノがネザーランド地方(オランダ、ベルギー周辺)アントワープに移住して、マジョリカの技法をオランダに紹介したのがはじまりです。
デルフト陶器のルーツは、16世紀にイタリアのマジョルカ出身の陶工グィド・ディ・サビノがネザーランド地方(オランダ、ベルギー周辺)アントワープに移住して、マジョリカの技法をオランダに紹介したのがはじまりです。
ベルギーとの国境近いオランダ南西部に位置するデルフトは、大小の運河が町を横切る緑あふれる小都市で、16世紀初期頃まではビールの醸造が主産業でしたが、16世紀中頃の2度の戦争による大火により、ビール生産が壊滅的な打撃を受けました。
その頃、アントワープなどの陶工たちが戦火を免れて、デルフトの地に移り住み、マジョルカ風の陶器やタイルの生産に従事したことにより、デルフト陶器の発展の基礎が築かれました。
デルフト陶器の初期の技法や装飾様式は、こういった経緯でイタリア・マジョルカと極めて類似していることから、専門家の間では、しばしばイタロ=フレミッシュや、ネーデルラント・マジョルカとも呼ばれます。
 デルフト陶器は、17世紀中頃に盛行しましたが、デルフトの地で陶器が急速に発達した理由としては、近郊に作陶に適した良質の陶土を大量に入手できたことと、いち早く陶工、陶画家、彫刻家らによりギルドが結成され、器形や装飾文様に新しい試みがなされ、作陶の技術に改良に貢献したことがあげられます。
デルフト陶器は、17世紀中頃に盛行しましたが、デルフトの地で陶器が急速に発達した理由としては、近郊に作陶に適した良質の陶土を大量に入手できたことと、いち早く陶工、陶画家、彫刻家らによりギルドが結成され、器形や装飾文様に新しい試みがなされ、作陶の技術に改良に貢献したことがあげられます。
デルフト陶器の初期は、マジョルカ風の明るい色絵の陶器を焼いていましたが、本格的な大航海時代に入り、ヨーロッパに中国磁器が輸入されるようになると、中国磁器を模倣した作品を盛んに作るようになりました。
 当時のヨーロッパでのやきものの技術は、中国や日本に比べて大きく立ち後れており、ヨーロッパの宮廷や支配階級の間では、極東から舶来する美しい白い地肌の磁器への関心は、宝石へのそれに勝るものともいわれ、特に中国磁器はヨーロッパの王侯貴族が争って、買い求めました。
当時のヨーロッパでのやきものの技術は、中国や日本に比べて大きく立ち後れており、ヨーロッパの宮廷や支配階級の間では、極東から舶来する美しい白い地肌の磁器への関心は、宝石へのそれに勝るものともいわれ、特に中国磁器はヨーロッパの王侯貴族が争って、買い求めました。
当時、中国からの舶来品の磁器の多くは、景徳鎮あたりでつくられた染付磁器で、デルフトでは、これを模倣して白地にコバルトの青色の染付で、景徳鎮窯の青花を描くようになりました。これはデルフト陶器がデルフト・ブルーといわれる所以ともなっています。
さらに、1670年以後は、ヨーロッパでスワトウ磁器と呼ばれた色絵磁器、続いて清朝の康煕五彩、日本の柿右衛門や伊万里焼色絵の鉢や皿を模した器を製作することによって、自国はもとより、ヨーロッパ諸国で人気を博しました。
こうした中国風もしくは日本風のシノワズリのやきものは、デルフト焼と呼ばれ人気となり、マッカムなど他の窯でもこれを真似るようになり、その後オランダで焼かれたシノワズリの陶器はすべてデルフト陶器と呼ばれるようになりました。
17世紀末になると、オランダ絵画をとり入れた作風と東洋的な作風が主となり,ヨーロッパの窯業を支配するほどデルフト陶器は、盛んになり、全盛期には、デルフトに100を上回る窯元があったといいますが、18世紀以降は、経済の悪化などにより次第に衰退へと向かいました。
 しかし、そのデルフト陶器の伝統は今も引き継がれています。現在は、唯一17世紀から残る窯元として、オランダ王立ロイヤル・デルフトがあります。
しかし、そのデルフト陶器の伝統は今も引き継がれています。現在は、唯一17世紀から残る窯元として、オランダ王立ロイヤル・デルフトがあります。
今でもロイヤル・デルフトでは、数世紀続いてきた伝統を守り、職人がひとつひとつ丁寧に手作業で絵付けする作品づくりを続けており、その高貴な美しさは現代陶器の愛好家の目を惹くものとなっています。
ロイヤル・デルフトの窯元は、一般公開されており、ミュージアムでデルフト・ブルー陶器のアンティークコレクションを鑑賞したり、工房で本格的な陶器の製造現場や職人らによる絵付けの工程などを間近に見ることができます。また、ワークショップで絵付け体験などもできるようになっており、庭園に面したティールームでは、アフタヌーンティーを楽しんだり、ショールームではデルフト陶器のコレクションを購入することができます。