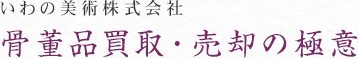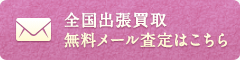やきものの源流である土器の歴史が12000年前と古いのに比べ、陶磁器を焼く焼成窯が日本に伝わったのは比較的新しく、5世紀頃の古墳時代と今から1500年ほど前です。窯の技法が伝来してからは陶磁器の技術は画期的に進歩しました。
先人達は、良いやきものをつくるために、高温で焼成するために必要な「窯」の研究を重ねました。構造の単純な古い窯であっても、優秀なものは最近まで使われています。ここでは、日本における代表的な窯の種類を紹介します。

 5世紀に朝鮮半島より伝わった日本最古の歴史を持つ窯です。従来の縄文土器、弥生式土器などは手捻り成形した土を「野焼き」していましたが、穴窯は傾斜地につくる地下式または半地下式のトンネル状の窯で焼成します。
5世紀に朝鮮半島より伝わった日本最古の歴史を持つ窯です。従来の縄文土器、弥生式土器などは手捻り成形した土を「野焼き」していましたが、穴窯は傾斜地につくる地下式または半地下式のトンネル状の窯で焼成します。
穴窯の燃料は木材(薪)ですが、焼成室を持つことで高温を得ることができ、条件が良いと1200℃以上にもなりました。
陶磁器などのやきものは、一般的には成形→素焼き→施釉→本焼きという工程ですが、穴窯の場合は成形・乾燥後に本焼きを行うので、薪の灰が自然に降りかかり、自然釉となります。現在でも信楽焼や備前焼などが同じ方法で焼かれています。
 連房式登窯とは、焼成室を斜面に複数連ねた窯の総称で、現在一般的に狭義の「登窯」と呼ばれているものです。16世紀後半に中国・朝鮮半島より唐津に伝わり、その後各地に広まった形式です。最古に属する唐津焼が焼かれたのが連房式登窯のはじまりとされています。傾斜地の下部に焼成室を設け、その上に複数の焼成室を階段状につなぎあわせています。
連房式登窯とは、焼成室を斜面に複数連ねた窯の総称で、現在一般的に狭義の「登窯」と呼ばれているものです。16世紀後半に中国・朝鮮半島より唐津に伝わり、その後各地に広まった形式です。最古に属する唐津焼が焼かれたのが連房式登窯のはじまりとされています。傾斜地の下部に焼成室を設け、その上に複数の焼成室を階段状につなぎあわせています。
従来の穴窯が単室だったのに対し、複数の焼成室がある登窯は、上からみると房(ふさ)の形をしているため連房式と呼ばれます。複数ある焼成室それぞれで燃料を燃やすため、熱効率に優れ、一度に大量につくることができます。
 錦窯(きんがま)は、上絵を焼きつけるための小型の絵付窯の代表的なもので、初期の上絵は「赤」を主体とした色絵具だった名残から赤絵窯ともいいます。その後、色絵具は赤・青・緑・紫・黄色といった色彩を増やした「錦手」となり、錦窯とも呼ばれるようになりました。
錦窯(きんがま)は、上絵を焼きつけるための小型の絵付窯の代表的なもので、初期の上絵は「赤」を主体とした色絵具だった名残から赤絵窯ともいいます。その後、色絵具は赤・青・緑・紫・黄色といった色彩を増やした「錦手」となり、錦窯とも呼ばれるようになりました。
 錦窯は器ものに直接炎を当てないように、外窯・内窯の2重構造になっています。こうした構造の理由は、直接火が当たるとススや焦げが生じたり、予期せぬ変形や窯変を伴うからといった理由からです。
錦窯は器ものに直接炎を当てないように、外窯・内窯の2重構造になっています。こうした構造の理由は、直接火が当たるとススや焦げが生じたり、予期せぬ変形や窯変を伴うからといった理由からです。
錦窯では、円筒形の窯の内側に上絵付をした器を重ねて詰め、手前にある焚き口から700〜800℃の低火度で短時間に焼成します。
温度が上がりすぎてしまうと、上絵が液状化してしまうので、当時は薪を使った温度管理に熟練を要しましたが、現在はガスや灯油、電気窯が主流となり、温度管理も容易となり、さらに温度設定や温度上昇パターンの選択など操作も簡単になりました。