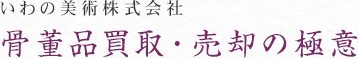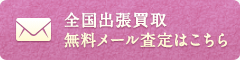日本の縄文式土器や須恵器などにみられるように、昔のやきものには、釉薬は使われておらず、無釉で焼成されていました。
日本の縄文式土器や須恵器などにみられるように、昔のやきものには、釉薬は使われておらず、無釉で焼成されていました。
この時代は素焼きに近い状態で、窯を用いずに焼成する野焼きの方法がとられていたと考えられています。

平地などを少し窪めて、そこに草木やもみ殻などを敷き、その上に成形した器を並べて、その上や周りに薪や藁などを積んで焼成していたとされています。
埴輪などが焼かれた飛鳥時代の須恵器には、焼成中に灰がかかり、熔けて自然灰の釉のかかったものもみられます。
また、草木を焼いた灰を水に溶いて、釉薬としてかけて焼いた土器などは、奈良・平安時代につくられました。平安時代に猿投古窯(愛知県) で生産された「白瓷」に灰釉を施した灰釉陶器が知られています。
 灰釉とは、草木や藁の灰を主原料とした高火度釉のことをいいます。
灰釉とは、草木や藁の灰を主原料とした高火度釉のことをいいます。
そもそも灰釉とは、上述したように、窯の中で薪などの灰が器の素地に降りかかり、熔けてガラス化した自然降灰による自然釉に着目したことから始まりました。
後に、自然にできた灰釉のメカニズムに、人々が気付き、人為的・人工的に灰を調合してつくりだしたのが、「灰釉」と呼ばれるものです。
日本ではこの灰釉がベースとなり、中国からの技術と相まって、様々な独自の釉薬が発達していきました。例えば、鉄を含んだ原料を使って黄瀬戸、銅を使って織部、白味を強調した志野などが例としてあげられます。
 灰釉の原料となる灰には、木灰すなわちイスノキ、カシ、クヌギ、クリ、マツなどのその皮を燃やした灰と、土灰、すなわち薪や炭などの雑木を囲炉裏などで燃やした灰、また藁やもみ殻などの灰があります。
灰釉の原料となる灰には、木灰すなわちイスノキ、カシ、クヌギ、クリ、マツなどのその皮を燃やした灰と、土灰、すなわち薪や炭などの雑木を囲炉裏などで燃やした灰、また藁やもみ殻などの灰があります。
灰は、原料となる木の種類が違えば、当然、灰にしたときの成分も異なり、また、木のどの部分を焼いた灰かであるか、どの季節に伐採された樹木かによっても、灰の成分が変わり、発色なども異なります。
 木などを燃やした灰は、ゴミやアク(灰汁)が含まれていて、そのままでは灰釉として使えないため、水簸します。
木などを燃やした灰は、ゴミやアク(灰汁)が含まれていて、そのままでは灰釉として使えないため、水簸します。
1. まず、灰をバケツに入れ、水を加えて全体を撹拌します。
 2. 浮いてきた燃え残りや炭をザルですくいとって、再び水を足して撹拌し、ザルですくうことを数回繰り返します。
2. 浮いてきた燃え残りや炭をザルですくいとって、再び水を足して撹拌し、ザルですくうことを数回繰り返します。
3. ゴミがおおかた取れたら、水をたっぷり入れてまた撹拌します。そのまま半日〜1日放置して灰を沈殿させ、上水を取り除き、再び水を加えて撹拌します。 この作業を1〜2週間繰り返します。
4.別のバケツを用意してふるいを渡し、撹拌した灰をふるいに通します。ふるいは、目の荒いものから徐々に細かいものへと、何段階かに分けて通していきます。この後、かごなどを利用して中味を開けて水を抜き、乾燥させます。