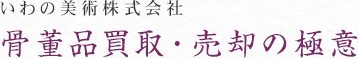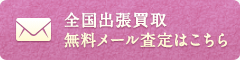器などの焼きものに対して、「瀬戸物(せともの)」という言葉が使われることがあります。瀬戸物(せともの)の瀬戸は、愛知県瀬戸市を指しており、この瀬戸の地は、古くから焼きものに適した良質な粘土に恵まれ、常滑・信楽・越前・丹波・備前と並び日本六古窯の産地としても知られています。
 瀬戸で産出される、木節粘土・蛙目粘土は世界でも有数の粘土であり、その特性を活用した瀬戸焼は、東日本で広く流通し、瀬戸物は陶磁器を指して一般名詞化しました。
瀬戸で産出される、木節粘土・蛙目粘土は世界でも有数の粘土であり、その特性を活用した瀬戸焼は、東日本で広く流通し、瀬戸物は陶磁器を指して一般名詞化しました。
瀬戸物(せともの)とは、もともと瀬戸の地域で作られた焼きものを指す言葉でしたが、転じて、俗にいう食器類のことを「せともの・セトモノ」というように使われるようになりました。つまり、瀬戸物という言葉は、現在では必ずしも瀬戸で作られたものに限らず、日本の焼きものの総称のように使われています。
平安時代〜鎌倉時代
 せとものは元来、瀬戸で作られていた焼きもの「瀬戸焼」のことですが、瀬戸での焼きものの歴史は諸説あり、伝説によれば宋(中国)で陶法を学んできた陶祖 加藤四郎左衛門景正が鎌倉時代に施釉陶器の技法を伝え、瀬戸で窯を築いたのが始まりとされています。しかし、実際には平安時代中期・広久手古窯跡群での灰釉が施された須恵器(灰釉陶器)が始まりとも伝わっています。
せとものは元来、瀬戸で作られていた焼きもの「瀬戸焼」のことですが、瀬戸での焼きものの歴史は諸説あり、伝説によれば宋(中国)で陶法を学んできた陶祖 加藤四郎左衛門景正が鎌倉時代に施釉陶器の技法を伝え、瀬戸で窯を築いたのが始まりとされています。しかし、実際には平安時代中期・広久手古窯跡群での灰釉が施された須恵器(灰釉陶器)が始まりとも伝わっています。
当時は、中国から輸入される磁器を模倣したものが代用品として生産され流通し、また鎌倉時代には、優美な印花文や画花文を施したものが多くみられました。
室町時代〜桃山時代・戦国時代
 室町時代に入ると椀、皿や鉢といった日用雑器の生産が増えますが、他に「古瀬戸」の生産が行われていました。古瀬戸は、瀬戸窯のみで生産された釉薬を器面全体に施した施釉陶器の総称です。
室町時代に入ると椀、皿や鉢といった日用雑器の生産が増えますが、他に「古瀬戸」の生産が行われていました。古瀬戸は、瀬戸窯のみで生産された釉薬を器面全体に施した施釉陶器の総称です。
この時代には、侘び茶が完成し、茶の湯の隆盛に伴い、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部などの瀬戸の茶器が茶人の鑑賞に十分耐えうる品格まで磨き上げられました。
戦国時代には瀬戸焼は、美濃などの各地でも焼かれるようになり、様々な形のせとものが焼かれ、灰釉ぐい呑・鉄釉皿・志野碗・瀬戸黒沓茶碗などが、古窯から発見されています。
江戸時代〜現代
江戸初期には、肥前の有田を中心にはじまった伊万里焼の磁器が急速に発展し、瀬戸焼・せとものの市場は奪われ、衰退していきました。 江戸時代後期には、九州で磁法を学んできた加藤民吉が瀬戸に戻り磁器生産を本格化しました。瀬戸では旧来の陶器を「本業焼」、磁器を「染付焼き(瀬戸染付)」と呼ぶようになりました。
 明治期に入り、海外にも多く瀬戸焼は輸出されるようになりますが、万国博覧会などにも積極的に出品し、高い評価を得ると、海外からの注文が多くなり、世界に瀬戸の名が広まりました。
明治期に入り、海外にも多く瀬戸焼は輸出されるようになりますが、万国博覧会などにも積極的に出品し、高い評価を得ると、海外からの注文が多くなり、世界に瀬戸の名が広まりました。
その後、戦争を経て、瀬戸窯業は戦災をほとんど受けなかったことなどから、戦後は急速に復興し、輸出が再開され、ディナーセットや磁器などが盛んに輸出されるようになりました。
元来、瀬戸での焼きものであったの瀬戸物(せともの)は、このような経緯を経て、陶磁器の代名詞となるまでとなり、現在は、瀬戸で焼かれたもの以外の器にも「せともの」という言葉が使われるようになりました。